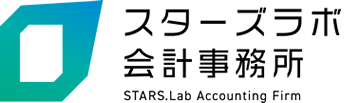多くの経営者は、「節税しながら将来のリスクにも備えたい」と考えています。そんなときによく検討されるのが、倒産防止共済です。掛金をそのまま経費として扱えるため、節税につながり、取引先が倒れた場合には事業継続の支えにもなります。
ただし、一見便利に見えても、注意すべき点がいくつかあります。そこで本記事では、倒産防止共済で節税するメリットと気をつけたいポイントについて、できるだけ丁寧にわかりやすく解説します。
目次
倒産防止共済とは?節税にも使える中小企業向け制度
倒産防止共済は、取引先が倒れたときに、資金繰りが急に悪化する事態を避けるために設けられた制度です。起業したばかりの方でも利用しやすく、事業の資金を安定させながら節税にもつなげやすいため、多くの企業で活用されています。
倒産防止共済の目的と特徴
倒産防止共済は、中小企業が取引先の急な倒産で資金繰りに行き詰まらないよう支える目的で、国(経済産業省)所管の中小企業基盤整備機構によって設けられています。法人でも個人事業主でも加入でき、掛金は月5,000円から20万円の範囲で自由に選べます。掛金は累計800万円まで積み立てられ、支払った金額をそのまま経費として扱える点が大きな特徴です。
また、掛金は契約途中で増減することが可能なため、起業初期の利益変動が大きい時期でも無理なく続けやすい制度といえます。資金の積み立てと節税の両方を同時に進められるため、創業期の不安を少しでも軽くしたい方に向いているといえるでしょう。

取引先が倒れたときの資金サポート
倒産防止共済に加入すると、主要な取引先が倒れた場合に、積み立てた掛金をもとに資金を借りることができます。具体的には、最大で掛金総額の10倍(上限8,000万円)まで借りられ、無担保・無保証で申し込むことが可能です。
そのため、急に売掛金が回収できなくなったときでも、事業を続けるための資金を確保しやすくなります。また、返済方法も比較的柔軟に設定されているため、「資金ショートだけは絶対に避けたい」と考える経営者にとって心強い制度といえるでしょう。
倒産防止共済で節税できる理由と仕組み
倒産防止共済が節税に役立つと言われるのは、掛金をそのまま費用として扱える点や、支払いと受け取りのタイミングを調整しやすい点にあります。ここでは、その理由を分かりやすく説明します。

掛金をそのまま経費にできる
倒産防止共済では、毎月支払う掛金をそのまま経費として計上できます。支払った掛金をその年の費用として扱えるため、利益が出た年に掛金を増やせば、その分だけ課税される所得を抑えることが可能です。
一般的な保険では、掛金の一部しか経費にできない場合がありますが、倒産防止共済は、全額を費用として扱える点が大きな特徴となります。そのため、起業初期の利益変動が大きい時期でも、年度ごとの状況に応じて負担を調整しながら節税につなげることができます。
納税の先送りといわれる理由
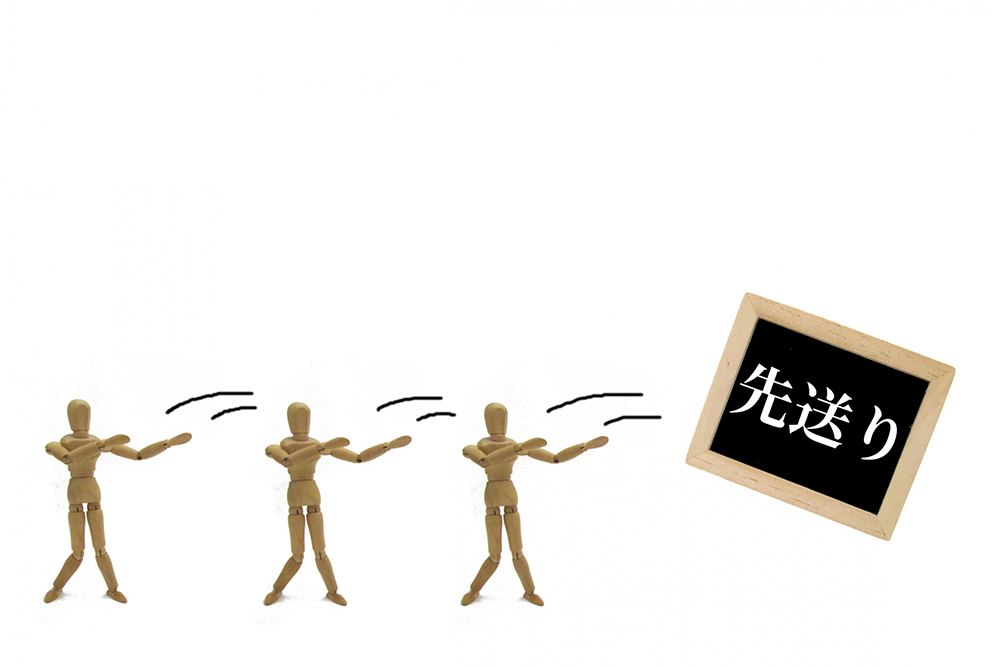
倒産防止共済は、節税に非常に効果的な制度ですが、税金そのものをなくすものではありません。掛金を払った年の所得は減りますが、解約すると受け取る金額が今度は所得として計上されるため、その時点で税金が発生します。そのため、正しくは、「節税」というより、「納税時期を後ろへずらす効果がある」ということになります。
ただし、この特徴を上手に活用すれば、節税することが可能です。例えば、黒字で税負担が重くなりそうな年に多めに掛金を払っておき、赤字が出ている年に解約すれば、結果として税負担が抑えられます。一方で、解約する年の利益次第では、受け取った金額が上乗せされて税金が増える可能性があります。
加入前に知っておきたいデメリットや注意点
倒産防止共済は便利な制度ですが、加入前に理解しておきたいポイントがいくつかあります。節税に使えるとはいえ、使い方を誤ると負担が増える場面もあるため、しっかりと確認しておきましょう。
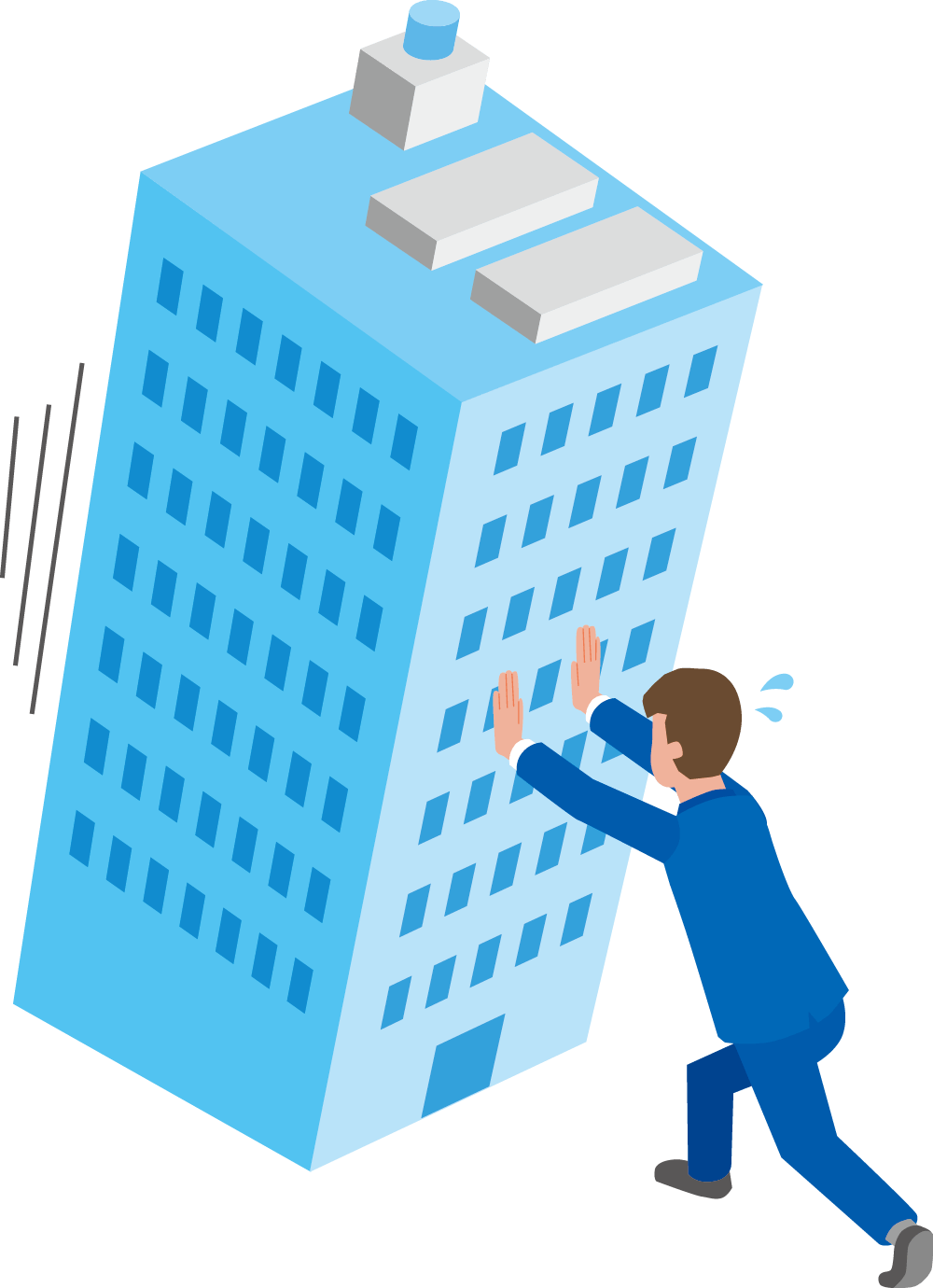
40ヶ月未満の解約は不利になりやすい
倒産防止共済では、加入してから40ヶ月以上経過しているかどうかで、解約時に戻ってくる金額が大きく変わります。40ヶ月未満で解約すると、払った掛金の全額は戻らないため、損をする可能性が高くなってしまいます。
したがって、短期間での解約を前提に使う制度ではないことを理解したうえで、ある程度の期間は積み立てを続けるつもりで加入しなければなりません。
短期解約と再加入に関する新たな注意点(2024年10月改正)
倒産防止共済は節税につながる制度ですが、2024年10月1日(2024年10月)から短期解約と再加入に関する新しいルールが加わっています。具体的には、2024年10月1日以降に一度解約した後、2年以内に再加入した場合、再加入後の掛金については損金または経費として扱うことができなくなりました。
この改正は、節税目的で短期解約と再加入を繰り返すことを防ぐためです。従来は、解約手当金の課税と新規加入の損金算入を組み合わせて節税効果を狙うケースもありましたが、改正後は同じ方法が使えなくなりました。
そのため、この制度を活用する際には、解約のタイミングと将来の加入予定を見据えて判断しなければなりません。
解約のタイミング次第で税負担が増えることも
倒産防止共済は、掛金を費用にできる点が魅力ですが、解約すると受け取る金額が所得として計上されます。つまり、解約した年の利益が大きいと、受け取った金額が上乗せされることで税負担が増える可能性があります。
例えば、事業が好調で利益が大きくなった年に800万円を解約して受け取ると、その800万円がそのまま所得に加わります。このケースでは、節税どころか、逆に税額が増える結果になりかねません。こうしたことから、解約する時期を意識することが非常に重要となります。
倒産防止共済を最大限活用するためのポイント

倒産防止共済は、積み立て方や解約のタイミングを意識することで効果が大きく変わります。最後に、倒産防止共済を最大限活用するためのポイントについて解説します。
掛金と解約時期を事業計画に合わせて考える
倒産防止共済を効果的に使うためには、掛金の設定と解約のタイミングを事業計画と合わせて考えることが重要です。利益が大きく出た年に掛金を増やせば、所得を抑えて税負担を軽くできます。
一方、解約すると受け取る金額がそのまま所得に加わるため、事業が好調なタイミングで解約してしまうと、税負担が大幅に増えかねません。したがって、将来的に利益が落ち着く見込みがある時期や、減価償却が多く発生する年など、所得が低くなるタイミングで解約するように、事業計画に基づいてあらかじめ解約時期を決めておくことが大切です。
掛金の前納を検討する
倒産防止共済の掛金は本来、毎月5,000円から20万円の範囲で支払うように定められていますが、希望すれば最大1年分をまとめて前払いできる「前納」という方法も選べます。前納した金額は、その年度の費用として扱われるため、決算期に利益が大きくなりそうな場合には、税負担を抑える手段として非常に効果的です。
ただし、前納をすると翌年度に回せる掛金が減るため、資金繰りや翌年以降の利益見通しを考えて慎重に判断しなければなりません。また、掛金月額を変更したうえで前納する場合は、別途の申出が必要です。
こうした判断は事業の状況によって変わるため、無理のない活用をするには税理士などの専門家に相談しながら検討するようにしましょう。
まとめ
倒産防止共済は、取引先の倒産による資金繰りの乱れを防ぎながら、掛金を費用として扱える非常に優れた制度です。ただし、40ヶ月未満の解約が不利になりやすいことや、受け取る金額が所得に加わる点には注意が必要です。
また、前納を使って決算対策に活かす方法もありますが、適切な判断には事業の状況を総合的に見る視点が欠かせません。こうしたことから、倒産防止共済のメリットを最大限引き出すためには、税理士などの専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。