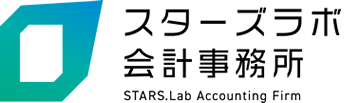赤字企業はもちろんのこと、黒字企業であっても、ある条件下では資金繰りが悪化してしまうことがあります。その結果、現金が不足し、給料などの支払いに影響を及ぼしてしまう場合も少なくありません。そこで本記事では、資金繰り悪化の前兆を示す指標や、経営者が早期に取るべき対策などについて解説します。
目次
資金繰り悪化の“兆候”は3つの指標で見抜ける

資金繰りの悪化は、ある時いきなり訪れるものではありません。そこでまず、資金繰りの異変を早期に察知するために確認すべき3つの指標について解説します。
現預金残高の推移で“減少のサイン”をつかむ
現預金残高は、会社の「生命線」ともいえる数字です。資金繰りの状況を確認するためには、単月の残高だけでなく、過去3~6ヶ月の推移を追わなければなりません。
そのうえで、売上が伸びているのに現預金が減っている場合は、売掛金の増加や在庫の滞留など、資金が一時的に社内で止まっている可能性があります。また、借入金の返済や設備投資による資金の流出も、現預金減少の原因となります。資金ショートを防ぐためには、毎月の残高推移をグラフ化し、減少傾向を早めに把握しておかなければなりません。
売掛金と支払サイトのバランスを点検する
資金繰りが悪化する多くの企業では、入金より支払いが先に来るケースが見られます。たとえば、売掛金の回収が60日後、仕入や外注費の支払いが30日以内であれば、30日分の資金ギャップが生じます。この差が積み重なっていくと、黒字でも資金が不足してしまうのです。
こうした状況を改善するためには、取引条件の見直しや、請求から入金までの期間を短縮する工夫が必要です。具体的には、仕入先や取引先と支払・回収条件を見直し、できる範囲で支払期日を調整するなど、キャッシュの動きを平準化する工夫が求められます。
資金繰り表で数字の流れを“見える化”する
資金繰り表は、現金の流れを可視化するための非常に効果的なツールです。売上や仕入の予定、借入返済、経費支払いなど、すべての入出金を時系列順に整理することで、将来の資金余裕や不足を事前に把握できます。
中小企業では、経営者自身が感覚的に資金を管理しているケースが多いため、実際の数値とのズレに気づかないことも珍しくありません。そのため、クラウド会計ソフトなどを積極的に導入し、自動で資金繰り表が作成できる環境を整えておけば、リアルタイムで資金の流れを把握しやすくなるでしょう。
資金繰りが悪化する3つのパターン
資金繰りが悪化する背景には、いくつかの共通点があります。ここでは、多くの中小企業が陥りやすい3つの典型的なパターンを紹介します。
売上が伸びても現金が増えない「黒字倒産型」

「売上が伸びているのに、なぜか現金が減っている」というのは、経営者が最も見落としやすい資金繰りの罠です。この主な原因は、利益計上のタイミングと現金の流れが一致していないことにあります。
たとえば、売掛金の回収が遅れたり、販売増に備えて仕入や人件費を先行させたりした場合、帳簿上は黒字でも手元資金は減少します。この状態が続けば、いずれ支払いや返済に行き詰まり、黒字倒産になりかねません。
したがって、経営を安定させるためには、損益計算だけでなく、キャッシュフローの視点からも資金の出入りを常に確認しておきましょう。
短期借入に頼りすぎる「返済負担型」

資金繰りが厳しい局面で、短期借入やカードローンなどに頼りすぎると、返済サイクルが早まり、慢性的な資金不足を招きかねません。とくに、設備投資や新規事業のように長期的な支出を短期融資で賄ってしまうと、最終的には返済が追いつかなくなってしまいます。
それを防ぐためには、資金の用途と期間を一致させることです。運転資金は短期融資で、設備資金は長期融資で、というように返済負担を平準化するようにしましょう。どうしても厳しい場合は金融機関と相談し、返済条件の変更(リスケジュール)などを検討することも効果的です。
税金や社会保険料を後回しにする「信用低下型」

資金が逼迫した時、支払いを後回しにしてしまいがちなのが、税金や社会保険料です。しかし、これを続けると、延滞税などの金銭的負担が増えるだけでなく、金融機関からの信用が著しく低下してしまいます。税金や保険料を滞納している企業は、追加融資や条件変更の審査で不利になるため、資金繰り改善のチャンスを失いかねません。したがって、どうしても納付が難しい場合は、できるだけ早い段階で税務署や年金事務所へ相談しておきましょう。
資金繰りを改善するための具体的な3つのアプローチ
資金繰りの悪化は、放置しておくと、経営の継続に悪影響を及ぼしかねません。したがって、できるだけ早めに手を打つことが大切です。最後に、中小企業でもすぐに実践できる3つのアプローチを紹介します。

支出の優先順位を見直し、固定費を削減する
資金繰り改善の第一歩は、支出の見直しです。家賃やリース料、人件費などの固定費は、収益に関係なく毎月必ず発生するため、これらの支出額を適正化することが大切です。契約の更新時期を確認したり、使用頻度の低いサービスや設備を見直したりするだけでも、月次の支出をある程度圧縮することができます。また、仕入れ単価や外注費の再交渉なども非常に効果的です。
ただし、支出を削減する際は、単に一律で削るのではなく、利益を生まないコストを中心にポイントを絞って実施しなければなりません。そのためには、経営者がコスト構造を正確に理解し、費用対効果を数値などで把握しておくことが大切です。
金融機関や専門家に早めに相談する
資金繰りが悪化し始めた段階で、金融機関や税理士など専門家に早めに相談することは非常に有効です。金融機関に対しては、試算表や資金繰り表などを用いて現状と今後の見通しを共有しておけば、追加融資や条件変更(リスケジュール)などの選択肢が検討できます。
なお、返済ができなくなってからでは対応が遅れる恐れがあるため、できるだけ早めに相談しておくと良いでしょう。事前に税理士などの専門家に相談しておけば、試算表の作成や資金調達のプランニングなども依頼できます。
補助金・助成金を活用して資金を確保する
資金繰りの改善には、返済不要の資金である補助金・助成金の活用も効果的です。業種や地域によって利用できる制度は多岐にわたりますが、事業再構築補助金や小規模事業者持続化補助金など、状況に合わせてさまざまな公的支援を活用することが可能です。
これらの補助金・助成金は、設備投資や販路拡大、人材育成など、多くの用途に使えるため、短期的な資金補填だけでなく、将来の収益基盤強化にもつながります。ただし、申請にあたっては満たすべき要件や締切があり、審査もあります。採択率を高めるためにも専門家と連携し、あらかじめ精緻な計画を立てておくと良いでしょう。
まとめ
資金繰りの悪化は、数字の変化を見落とすことから始まります。したがって、日々の現預金や回収・支払の動きを把握し、早めに対策を講じることが重要です。税理士などの専門家へ相談しておけば、現状に合った最適な資金改善策が提示してもらえるでしょう。