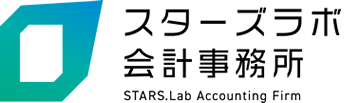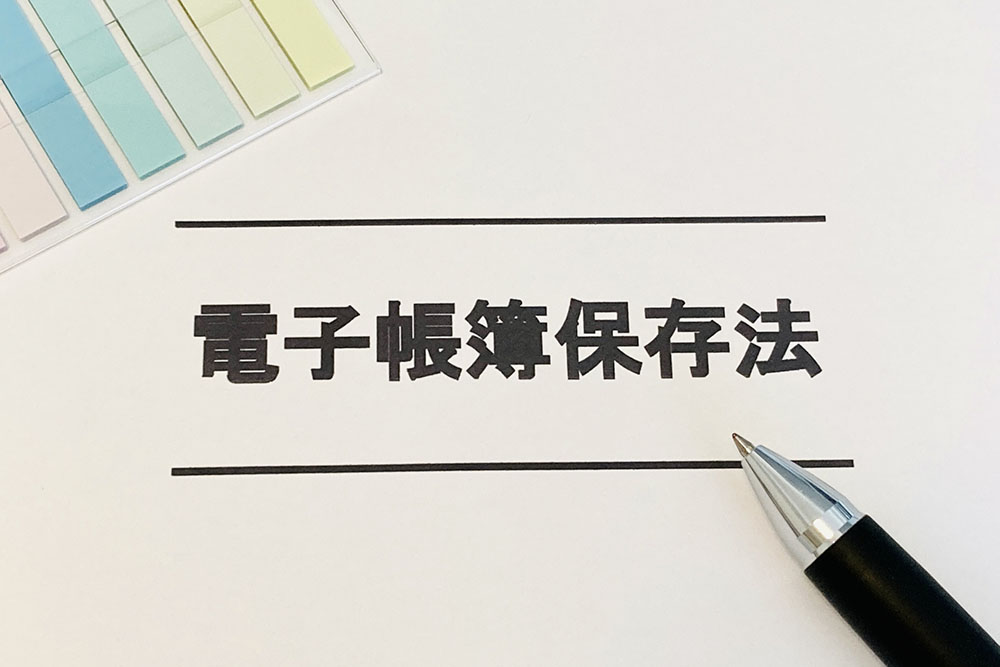
2024年から電子帳簿保存法のルールが完全に義務化され、電子で受け取った請求書や領収書などを適切に保存することが事業者に求められるようになりました。こうした変更により、起業したばかりの方でも対応が必要になる場面が増え、「自分も対象なのか」「何から始めれば良いのか」と戸惑う場面も増えてきました。
そこで本記事では、電子帳簿保存法の基本や義務化されたポイントを整理しながら、起業初期から無理なく取り組める準備や管理の方法を初めての方でもわかるように解説します。
電子帳簿保存法とは?2024年から何が義務化されたのか
はじめに、電子帳簿保存法の基本的な仕組みと、2024年から完全に義務化された内容について整理してみましょう。
電子帳簿保存法はどのような法律なのか
電子帳簿保存法とは、請求書や領収書、帳簿などの経理関係書類を、電子データで適切に保存するためのルールを定めた法律のことです。これまで紙で保存していた書類も、電子データで受け取るケースが増えたことから、税務調査時に内容を正しく確認できるように保存方法を整えることを目的としています。
この法律には「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」という三つの保存方法があります。それぞれに決められたルールがありますが、起業したばかりの方が特に関係しやすいのが、電子取引です。
電子取引とは、メールやクラウドサービスを通じて受け取る請求書や領収書などのデータのことを指し、今の事業運営では、ほとんどの方が利用する場面が多くなっています。

電子帳簿保存法の対象者
電子帳簿保存法の対象者は、帳簿や証憑の保存義務があるすべての事業者です。これは、株式会社や合同会社などの法人だけでなく、個人事業主、フリーランス、副業で事業を行っている方も含まれます。
事業規模の大小や従業員数に関係がないため、経営者一人の小さな会社でも、法律の内容を理解しておかなければなりません。特に請求書や領収書をPDFで受け取ることがある場合は、電子データの保存方法を整えておくことが必要です。
2024年1月から義務化された電子取引データの保存
2024年1月からは、電子取引で受け取った書類を電子データのまま保存することが義務化され、従来のように紙へ印刷して保存する方法は原則として認められなくなりました。電子取引とは、メールで送られてくるPDFの請求書、オンラインショップの領収書、クラウドサービスの利用明細など、電子的にやり取りされるすべての取引情報を指します。

また、保存する際には、日付や取引先、金額を検索できる状態にしておく必要があり、単にフォルダにまとめるだけでは要件を満たせない場合もあります。そのため、起業初期から電子データを整理しながら保存する意識を持っておかなければなりません。
義務化に対応するために必要な3つの準備
次に、電子帳簿保存法に対応するために必要となる、3つの準備について解説します
1.保存要件を理解して最小限のルールを決める
電子取引のデータを保存する際には、いくつかの決まりごとを満たす必要があります(ただし、前々年度の売上が5,000万円以下の事業者や、税務署からダウンロードに応じられる場合は一部緩和があります)。その中でも大切なのは、後から内容を確認しやすい形で保存しておくことです。
対応方法としては、ファイル名に「YYYYMMDD_取引先_金額」といった情報を入れるか、索引簿を作成する方法があります。まずはこの保存要件を理解し、負担のない範囲でルールを決めておきましょう。
2.クラウド会計や対応ツールを早めに導入する
電子データの保存を一つずつ手作業で行うと手間がかかり、保存漏れも起こりやすくなります。そのため、電子帳簿保存法に対応したクラウド会計ソフトやアプリを利用するよいでしょう。
これらのツールは、受け取ったデータを自動で取り込んだり、検索しやすい形で保存してくれたりと、必要な要件を満たしやすい仕組みが整っています。起業初期から導入しておけば、書類の整理にかける時間を大きく減らすことができるでしょう。
3.少人数でも保存方法を統一しておく
1人で事業を行っている場合でも、データの保存方法がその時々で変わると、後から探しにくくなったり、必要な書類が見つからなくなったりします。ましてや複数人で作業をする場合は、なおさら注意が必要です。
そこで、どこに保存するか、ファイル名をどう付けるかなど、基本的なルールを社内で簡単に決めておくとスムーズに管理できます。作業手順がばらばらになると、保存漏れや要件不足につながりやすいため、少人数のチームでも同じ方法で保存するようにしましょう。
起業初期でも簡単にできるデジタル管理のコツ
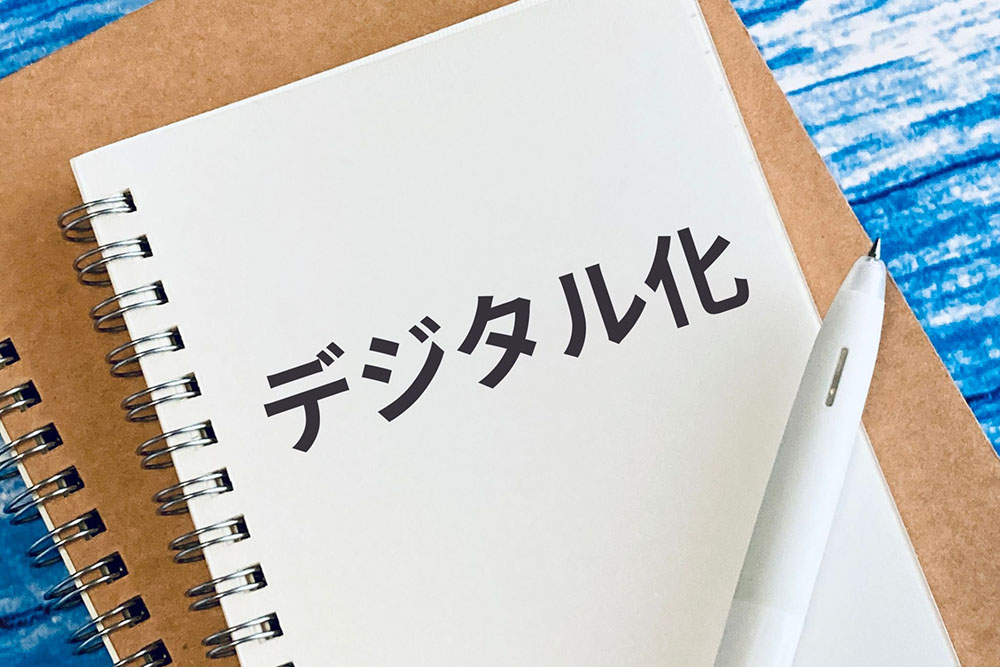
電子データの保存は、難しい作業をしなくても、日頃のちょっとした工夫で効率よく進められます。ここでは、起業したばかりの方でもすぐに取り入れやすい、実践的な管理のコツを紹介します。
受け取ったデータはその日のうちに保存する
電子で届いた請求書や領収書を後回しにすると、どこに保存したのか分からなくなったり、必要なデータを探すのに時間がかかったりします。保存を忘れると、要件を満たした形で残せなくなる可能性もあるため、受け取った日や作業した日にそのまま保存する習慣をつけることが大切です。
メールで届いたPDFやオンラインショップの明細などは、専用のフォルダにまとめて入れておくだけでも管理がしやすくなります。毎日の小さな積み重ねが、後から慌てないための一番のポイントになります。
ファイル名とフォルダを統一して分かりやすく整理する
電子データを整理する際には、ファイル名とフォルダの付け方を一定のルールにそろえておくと、必要な書類をすぐに見つけられます。たとえば、「日付」「取引先名」「金額」などの情報を入れておくと、検索しやすくなるだけでなく、整理にも時間がかからなくなります。
また、フォルダも取引内容や月ごとに分けるなど、後から見返したときに分かりやすい形にしておくと便利です。このように、見た瞬間に内容が分かる工夫をしておくだけで、電子帳簿保存法の要件も満たしやすくなります。
電子帳簿保存法対応でやってはいけないNG管理例
電子データの保存方法を正しく理解していないと、気付かないうちに要件を満たせない形で保管してしまうことがあります。ここでは、起業初期の方がやりがちなNG例を紹介します。

電子データを紙に印刷して保存してしまう
電子で受け取った請求書や領収書を紙に印刷して保管する方法は、2024年から原則として認められなくなっています。たとえば、メールで届いたPDFの請求書などを印刷してファイルに閉じただけでは、電子帳簿保存法の要件を満たした保存とは扱われません。
したがって、電子データで受け取った書類に関しては、電子データのままで保存しなければなりません。
メール受信箱に領収書やPDFを放置してしまう
忙しいときに、領収書や請求書のPDFをメールの受信箱にそのまま残してしまうことは珍しくありません。しかし、そのままにしておくと保存漏れが起きたり、後から必要なデータを探すのに時間がかかったりする原因になります。
電子帳簿保存法では、日付や取引先、金額を確認できる状態で保存する必要があるため、受信箱に置きっぱなしでは要件を満たせない場合があります。そのため、メールで届いた書類は、受け取ったタイミングで専用フォルダに移し、ファイル名を分かりやすく付けておきましょう。
フォルダやファイル名が統一されず検索できない状態になる
電子データを保存していても、フォルダの分け方やファイル名がばらばらだと、必要な書類を探しにくくなります。電子帳簿保存法では、日付、取引先、金額を検索できる状態にしておくことが求められているため、整理されていない保存方法では要件を満たせない可能性があります。
たとえば、ファイル名に日付や取引先名が入っていなかったり、保管場所が毎回違ったりすると、後から作業が重くなるだけでなく、税務調査の際にも確認が難しくなりかねません。したがって、最初から簡単なルールを決めておき、簡単に検索できるようにしておきましょう。
まとめ
電子帳簿保存法の義務化によって、電子データを正しい形で保存することが事業者に求められています。日々の整理を工夫することで進められる部分もありますが、保存要件には細かい決まりがあるため、判断が難しい場面も少なくありません。そのため、電子データの扱い方やルールづくりに不安がある場合は、早い段階で税理士などの専門家に相談しておくと良いでしょう。