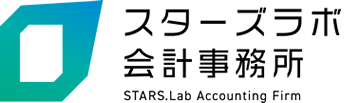「家族を社員にすると節税になる」という話を耳にしたことがありますか?たしかに、家族に給与や役員報酬を支払い、その分を経費として計上すれば、課税所得を減らすことは可能です。ですが、これは単純に「家族に給料を払えば良い」というものではありません。所得税法や法人税法では、家族を社員にするための条件や手続きなどが定められているため、誤った方法で処理をすると、税務リスクを抱えてしまいかねません。
そこで本記事では、個人事業主と法人それぞれの制度を比較しながら、家族を社員にした場合の節税の仕組みや注意点について解説します。
目次
家族を社員にすると本当に節税になるの?
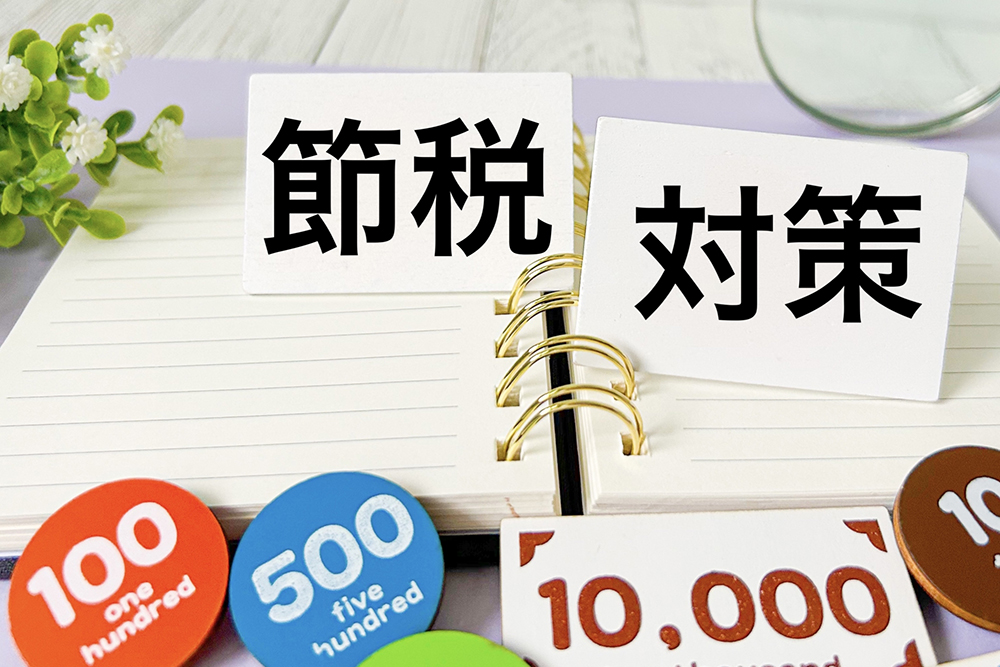
家族を社員として雇い、給与や賞与を支払うと、その金額は事業の経費(法人の場合は損金)として計上されます。経費が増えれば事業の利益は減少し、その結果として課税所得も小さくなるため、最終的に支払う税金が軽くなるわけです。つまり、家族を社員にすると、税負担を和らげる節税可能性があるのです。
ただし、「家族に給料を払えば必ず節税できる」という単純なものではありません。「実際に働いているか」「支給額が世間水準に比べて妥当か」など、税法上のルールに従っていることが重要になります。もし条件を満たさないまま給与を計上すれば、税務調査で否認されるため、かえって追徴課税などのリスクを負うことになりかねません。
家族に支払う給与が経費になる条件とは?
上述のように、家族に給与を支払えば必ず経費にできる、というわけではありません。そこで本章では、個人事業主と法人の場合に分けて、主な条件を整理します。

個人事業主の場合(専従者給与の要件)
青色申告の個人事業主が家族に給与を支払い、それを経費として計上するためには、対象となる家族が青色事業専従者でなければなりません。これにはいくつかの条件があります。まず、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に提出しておくことです。
次に、給与を支払う家族は、事業主と生計を一にする15歳以上の配偶者や親族であり、1年のうち6ヶ月以上その事業に専ら従事していなければなりません。さらに、実際に労務を提供していることが不可欠で、金額も世間一般の給与水準に比べて妥当でなければなりません。
なお、白色申告の場合は「事業専従者控除」となり、経費算入の額は最高でも年間86万円と定められているため、青色申告の場合と比べて自由度はかなり低くなります。
法人の場合(親族役員報酬・給与の要件)
法人で家族に給与や役員報酬を支払う場合、基本的には「損金」として認められますが、こちらも条件があります。まず、役員に対しては、原則として「定期同額給与」であることが必要です。つまり、毎月同じ金額を定期的に支給する必要があり、利益が出たからと言って途中で大きく増減させることはできません。賞与を支給する場合は「事前確定届出給与」として、事前に税務署に届け出をしなければなりません。さらに、実際に労務を提供していることも必要です。
単に「名義だけの役員」にして報酬を支払ったとしても、税務上は損金算入が否認される可能性があります。社員として雇用する場合も同様で、雇用契約書を整え、給与計算や社会保険手続きなどを適切に行っていることが前提となります。
このように、個人事業主と法人ではルールや手続きが異なりますが、共通して言えるのは「実態が伴っていて、金額が適正であること」が経費算入の大前提である、ということです。
節税目的だけで家族を雇うとどうなる?リスクと注意点

「家族を社員にすれば節税できる」という考え方は、ある意味で正しいものの、「節税目的だけ」で雇うと税務や社会保険の面で大きなリスクを抱えることになります。ここでは、代表的な注意点を整理します。
税務リスク
最も大きなリスクは、実態が伴わない場合に経費算入を否認されることです。例えば、働いていない家族に給与を支払ったことにして経費に計上した場合、税務調査で指摘されれば経費として認められません。そうなれば、過去にさかのぼって税額が修正されるだけでなく、追徴課税や重加算税といったペナルティも課される可能性があります。また、給与額が同規模の同業他社と比べ、常識的な水準を超えている場合も「過大」と判断され、認められないケースがあります。
社会保険・労務管理上のリスク
家族を社員として雇うと、場合によっては健康保険や厚生年金などの社会保険に加入する義務が発生します。すると、事業主側と家族側の双方で保険料負担が生じるため、結果的に節税効果よりも負担が増えてしまうことがあります。
また、配偶者を社員にすると、これまで扶養に入っていた社会保険から外れるため、家計全体での負担増につながるケースも少なくありません。さらに、労働契約や給与計算の整備が不十分だと「偽装雇用」と疑われ、行政から指摘を受けるリスクもあります。
このように、家族を社員にすることは一定の節税効果をもたらす可能性がある一方で、安易に形式だけ整えてしまうと、税務署や社会保険の調査で大きな不利益を被る恐れがあります。節税を目的にするのではなく、あくまで「実際に労務を提供している家族に正当な給与を支払う」ということでなければなりません。
適正な給与設定と手続きの流れ
家族を社員として雇う際に重要なのは、「いくらの給与を支払うか」と「どのような手続きを経るか」です。節税効果ばかりを追うと、税務署に否認されたり、社会保険の負担増でかえって損をしたりする可能性があります。そこで最後に、個人事業主と法人それぞれの場合に分けて、適正な給与設定と手続きの基本的な流れを解説します。

個人事業主の場合の流れ
個人事業主(青色申告)が家族に給与を支払う場合は、まず「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しなければなりません。提出期限は原則としてその年の3月15日までですが、開業初年度は開業日から2か月以内が期限となります。この届出を出していないと、その年は、専従者給与は一切経費にできません。
次に、届出後は、実際の勤務内容としてふさわしい給与額を決定し、給与明細を作成しながら定期的に支給します。支払い方法は現金でも銀行振込でも構いませんが、証拠として残る振込が望ましいでしょう。
また、帳簿には給与の支給額と日付を正確に記録し、年末には源泉徴収や法定調書の提出を行う必要があります。
法人の場合の流れ
法人で家族を役員や社員にする場合は、まず役員報酬であれば株主総会や取締役会での決議が必要です。この議事録を残すことが、税務署に対して「正式に決定された報酬」であることを示す証拠となります。役員報酬は「定期同額給与」でなければ損金算入が認められないため、月ごとに同じ金額を支給することが基本です。
一方、社員として雇う場合は雇用契約書を取り交わし、就業規則に基づいた(勤務内容に即した)給与額を設定します。その後は、給与計算ソフトなどを用いて給与明細を作成し、毎月の源泉徴収と社会保険料の控除を行います。社会保険や雇用保険の加入手続きも欠かせません。
共通の実務ポイント
個人事業主と法人に共通するのは「給与額が適正かどうかを客観的に説明できること」です。同業他社の水準や求人票の相場などを参考にしたり、労務内容に応じた金額を合理的に設定したりすることが必要です。支給は可能な限り銀行振込で行い、給与明細や帳簿を毎月整備しておくことが重要です。これらの記録があれば、税務調査の際にも正当性を裏付ける材料となります。
まとめ
家族を社員にすると、課税所得を減らし、税金負担を軽くする効果があります。ただし、その効果を得るためには、税務上のルールを守り、実際に労務を提供していることを前提としたうえで、給与額や報酬額を適正に設定しなければなりません。
一方で、条件を満たさずに形式だけ整えると、税務署による否認や追徴課税や社会保険料の負担増など、かえってリスクを招く可能性もあります。心配な方は、税理士などの専門家に相談しながら給与額の設定や必要な手続きを進めて行くと良いでしょう。