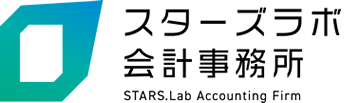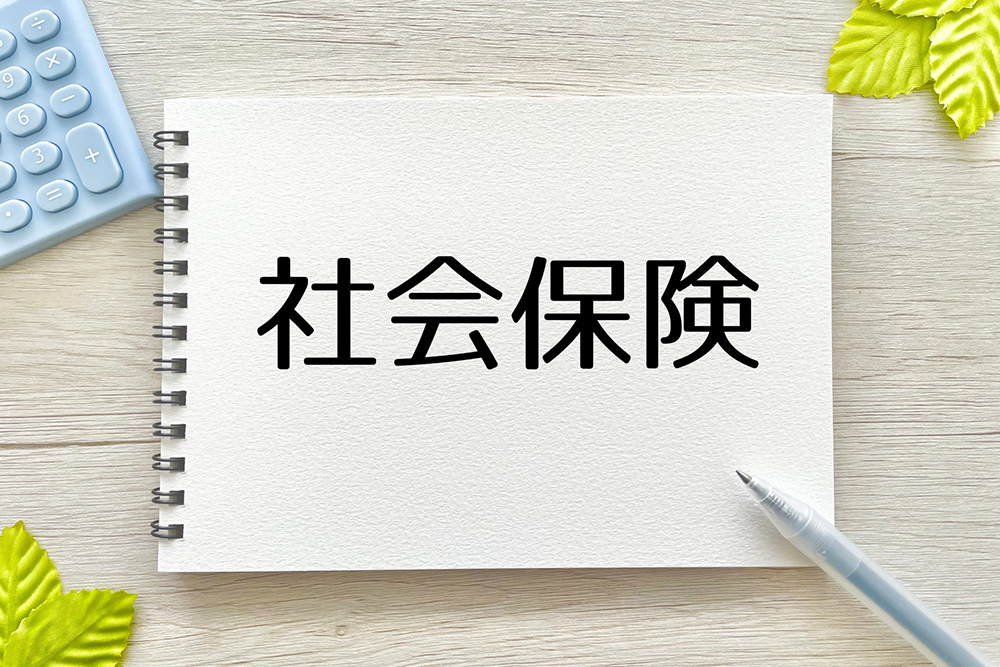
会社設立直後は、事業の立ち上げで何かと忙しく、社会保険の手続きは後回しになりがちです。しかし、法人は原則として社会保険への加入が義務付けられており、手続きを怠ると後々追徴課税などのリスクを招く可能性があります。
そこで本記事では、社会保険の基本的な仕組みから、加入のメリット、注意点、そして保険料負担を軽減する方法まで、会社設立後に必要な情報を分かりやすく解説します。
目次
社会保険の基礎知識
会社を設立したら、社会保険への加入は原則必須です。まずは、社会保険の基本的な仕組みと、法人が加入すべき理由をしっかりと理解しておきましょう。
社会保険とは何か
社会保険とは、病気、ケガ、老後、失業といった、私たちの生活における様々なリスクに備えて、国が運営する公的な保険制度のことです。会社員や公務員が加入し、給与から保険料が天引きされる形で、万が一の際に生活を支える役割を果たします。
会社を設立して法人となると、そこで働く役員や従業員は、一定の条件の下でこれらの社会保険に加入する義務が生じます。
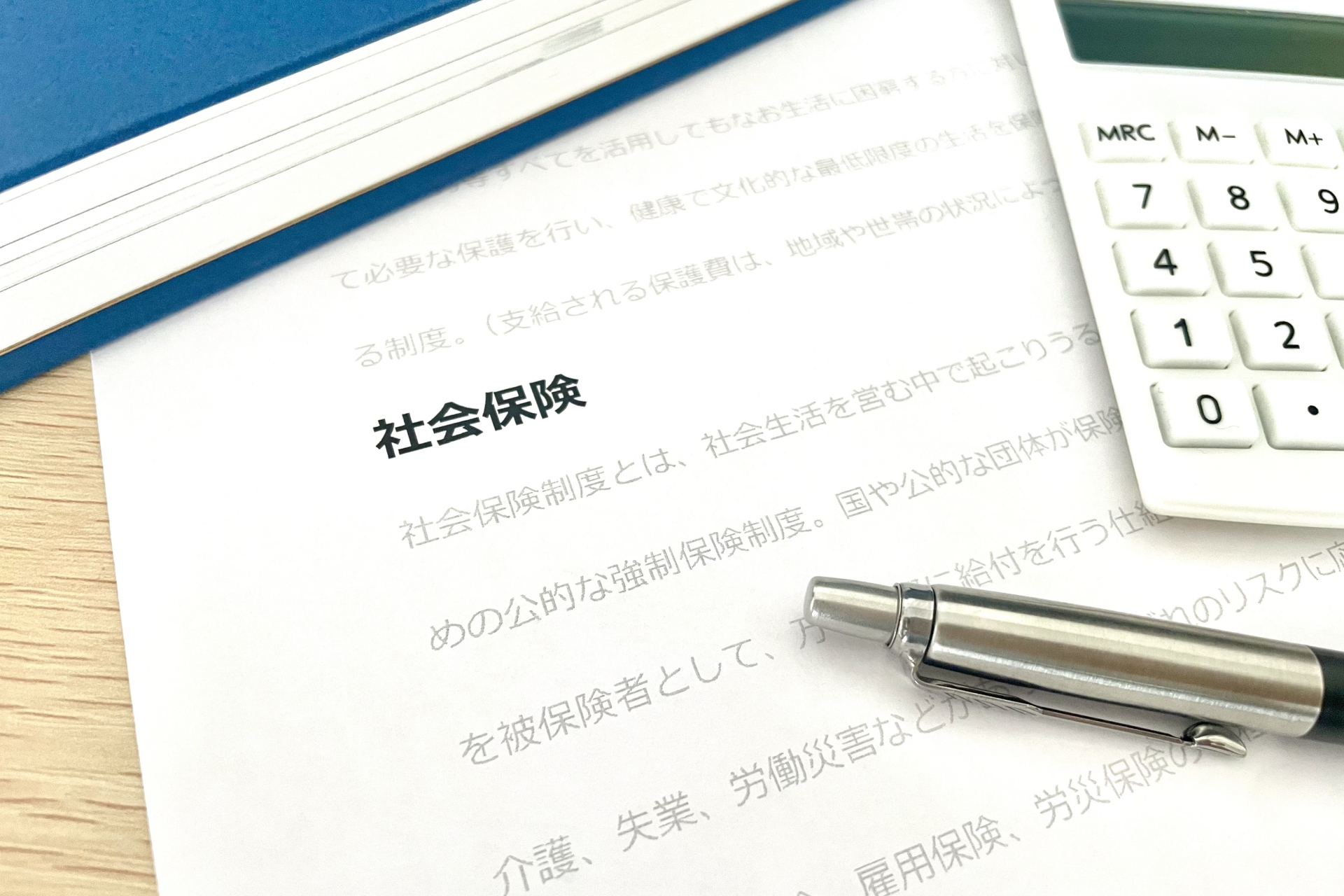
社会保険の5つの種類
社会保険には、以下の5つ種類があります。
- 健康保険・・・業務外の病気やケガの治療費を補助する医療保険。出産や休業時の手当も支給。
- 厚生年金保険・・・老後の生活を支える公的な年金制度。国民年金に上乗せして、より手厚い保障を提供。
- 介護保険・・・介護が必要になった際に、介護サービスの費用を補助。40歳以上の人が対象。
- 雇用保険・・・失業した際の生活を支援する失業給付を支給。再就職支援も実施。
- 労災保険(労働者災害補償保険)・・・業務中のケガや病気を補償。労働者の保護を目的とする保険なので、会社が全額負担する。
これらの5つを総称して、「社会保険」と呼びます。
法人が加入義務を負う理由
会社を設立すると、たとえ社長1人だけの法人であっても、原則として社会保険への加入が義務になります。これは、法人が「組織」として国に認められているためで、たとえ実態が個人事業に近い状態であっても、法律上は例外が認められていません。
個人事業主であれば、従業員が常時5人未満であれば加入義務がない業種もありますが、法人はこれに関係なく強制加入です。また、社会保険は従業員にとっての生活保障でもあるため、未加入のままにしておくと後から保険料をまとめて請求されるリスクもあります。
そのため、会社設立後は速やかに加入手続きを行わなければなりません。
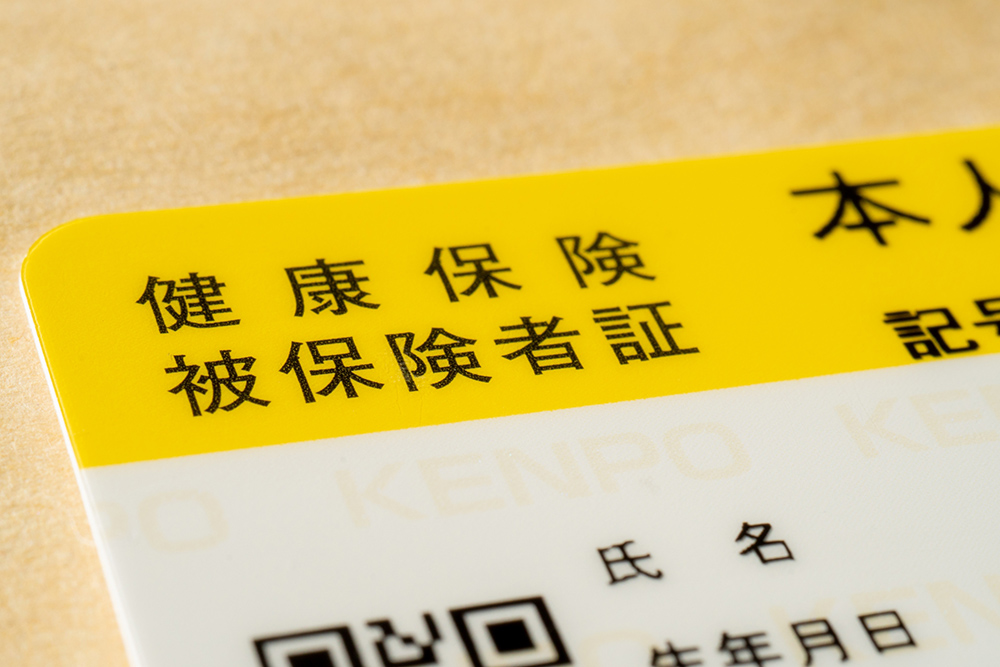
社会保険に加入するメリットとデメリット
社会保険への加入は、従業員や会社にとってさまざまなメリットがあるとともに、いくつかのデメリットもあります。
まずは、従業員のメリットです。
- 安心感の向上・・・医療、年金、失業給付など、万が一の事態に備えた手厚い保障により、安心して働くことができます。
- 将来の保障・・・厚生年金への加入は、将来受け取れる年金額を増やし、老後の生活を安定させます。
- 信頼感の向上・・・社会保険完備は、企業への信頼感を高め、長期的なキャリア形成を促します。
これに対し、従業員のデメリットは以下の通りです。
- 手取り額の減少・・・社会保険料が給与から控除されるため、手取り額が減少する可能性があります。
次は会社側です。会社のメリットは、以下のようになります。
- 人材の確保と定着・・・充実した福利厚生は、優秀な人材の確保と従業員の定着に繋がります。
- 企業イメージの向上・・・社会保険完備は、企業の社会的信用を高め、金融機関からの評価にも良い影響を与えます。
- 従業員のモチベーション向上・・・従業員が安心して働く事で、会社の信頼度があがり、業績アップにも繋がります。
これに対し、会社のデメリットは以下の通りです。
- 保険料の負担・・・従業員数が増えるほど、会社が負担する社会保険料の総額も増加します。
- 報酬設計の慎重さ・・・報酬額に応じて保険料が変動するため、役員報酬や給与の設計には慎重な検討が必要です。
- 事務処理の負担増大・・・社会保険に関する事務処理が増えることによって、事務処理の負担が増大する。
知らないと損!社会保険料の節約方法
社会保険料は会社と従業員が半分ずつ負担しますが、会社にとっては大きな固定費となるため、少しでも負担を軽くしたいと考える経営者は多いでしょう。そこで最後に、合法的な範囲で負担を軽減し、経営の安定化を図るための節約方法について解説します。
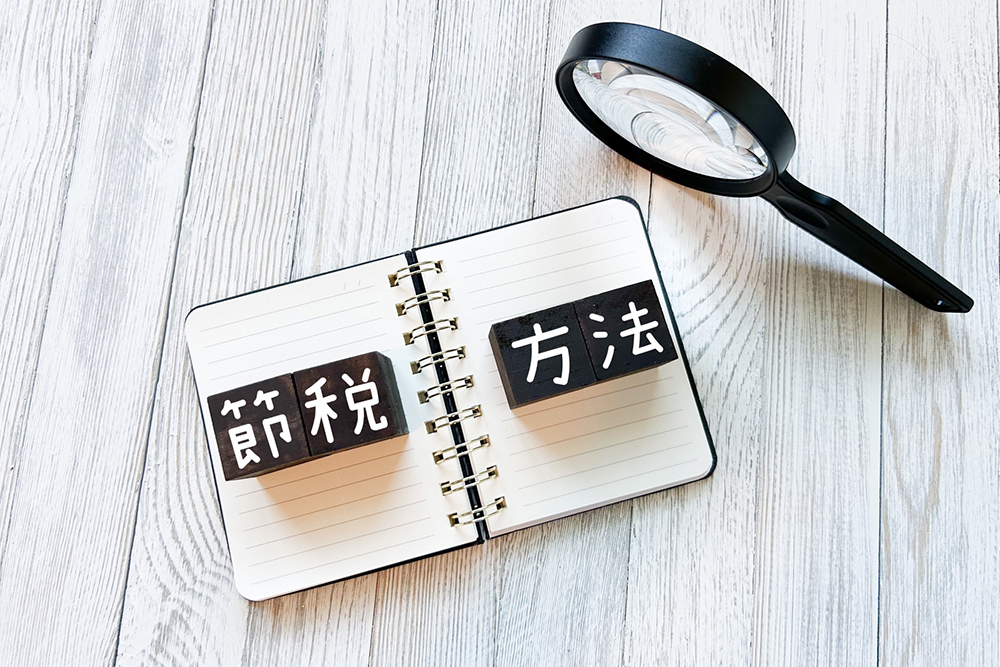
1. 役員報酬の見直し
社会保険料は、役員報酬の金額に基づいて算出されます。そのため、報酬額を調整することで、社会保険料の負担を軽減することが可能です。
しかし、役員報酬を不当に低く設定すると、税務上の問題や金融機関からの評価に悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、同業他社の役員報酬や、会社の規模・業績などを考慮し、税務署に説明できる合理的な金額を設定するようにしましょう。
2. 人員体制の見直し
業務の一部を外注化することで、社会保険の加入対象となる従業員を減らし、社会保険料の負担を軽減できます。しかし、外注と雇用は法律上区別されているため、形式的に外注契約を結んだだけでは、社会保険料の負担軽減にはなりません。
そのため、指揮命令関係の有無や報酬の支払い方などを考慮し、外注と雇用を明確に区別しておかなければなりません。
3. 法定福利費の見直し
法定福利費には、社会保険料以外にも、通勤手当や住宅手当などが含まれます。これらの費用を見直すことで、社会保険料の負担を軽減できる場合があります。また、国や自治体の助成金や補助制度を活用することで、会社の負担を軽減することも可能です。
4. パートタイマーの労働時間調整
パートタイマーの労働時間を調整することで、社会保険の加入義務を回避し、社会保険料の負担を軽減できます。しかし、労働時間を短くすると、従業員のモチベーション低下や人材不足につながる可能性があるため注意が必要です。
なお、パートタイマーに対する社会保険の加入義務は会社の従業員数や週あたりの労働時間によって異なるため、慎重に検討しなければなりません。
5. 専門家への相談:最適な節約プランの立案
社会保険料を節約するためには、専門的な知識が不可欠です。そのため、社会保険労務士や税理士などの専門家に相談し、自社の状況に合った最適な節約プランを立案してもらうようにしましょう。
社会保険料の節約は、法律や規則に従って行わなければなりません。違法な手段を用いると、追徴課税などのリスクが生じる可能性があります。したがって、必ず専門家と相談し、合法的な範囲で節約方法を検討するようにして下さい。
まとめ
社会保険は、会社を設立したあとに必ず向き合わなければならない大切な制度です。手続きをしないままにしていると、あとになって多額の保険料をまとめて請求されることもあります。
そのため、社会保険のしくみや必要性を正しく理解したうえで、自社の状況に合った形で取り組むことが大切です。不安な点や分かりにくい部分があれば、無理に一人で抱え込まず、社会保険の制度に詳しい専門家に相談しながら、安心して進めていくようにしましょう。