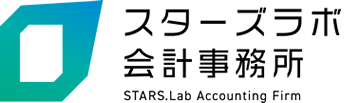起業を志す人にとって、「どれくらいの確率で成功できるのか?」は、非常に大きな関心事ではないでしょうか。実際に、どれくらいの確率で成功できるのかを知らないままで事業を始めてしまうと、資金計画や販売戦略が感覚頼りになり、思わぬ落とし穴にはまってしまいかねません。
そこで本記事では、中小企業白書などの統計資料のデータをもとに、日本における起業の成功率がどれくらいなのかを整理したうえで、失敗の主な原因とその回避策について解説します。
目次
そもそも「起業の成功」とは何か

何をもって「起業の成功」とするのかは、人によってその定義が異なります。一般的には、売上や利益が安定していることや、一定期間事業を継続できていることが、客観的な成功の指標とされます。
例えば、中小企業庁「中小企業白書」によれば、日本の創業1年後の生存率は約95.3%、3年後は約88.1%、5年後でも約81.7%とされています。約2割は5年以内に廃業しているわけですから、創業から5年以上事業を続けている企業は、おおむね成功していると判断することができるでしょう。
一方で、「経営者自身の満足度」や「やりがい」など、主観的な要素も無視できません。利益が出ていても、過度なストレスや生活の質の低下があれば、それを成功と呼べるかは疑問です。
たとえば、飲食店を経営している人が年商1億円を達成していても、休みがほとんど取れず家族との時間を失っていれば、本人の幸福度は低い可能性があります。逆に規模は小さくても、安定した利益と働きやすい環境を確保していれば、経営者にとっては十分な成功です。
したがって、自分自身の「起業の成功」を定義する際には、数字で測れる側面と、経営者の価値観に基づく側面の両方を意識してゴールを設定することが重要となります。
統計で見る起業の成功率と廃業率
統計データから、日本における起業の成功率と廃業率の現状を詳しく確認します。

創業後の生存率と業種別の傾向
上述のように、中小企業庁「中小企業白書」によれば、日本企業の創業5年後の生存率は、約80%です。一方、海外では米国や欧州の一部で5年後の生存率が50%前後にとどまる国もあることから、日本における創業後の生存率は国際的にも高い水準を保っていると言えるでしょう。
ただし、この数字は平均値であり、業種ごとに差があります。製造業やB to B型ビジネスは契約期間が長く既存顧客との関係が安定しやすいため、比較的継続率が高めです。
一方、小売業や飲食業は新規参入が多く競争が激しいうえ、原材料価格や立地条件に業績が左右されやすいため、生存率は低くなる傾向にあります。
廃業理由と海外との比較から見える課題
同白書によると、廃業理由の上位は、「収益性の悪化」「後継者不足」「健康上の理由」です。特に後継者不足は、日本特有の課題として指摘されています。
欧米では事業を売却したり業態転換したりして継続させる事例が多く見られますが、日本では廃業を選ぶ企業が多く、これが起業の長期的な成功率を押し下げています。また、日本の中小企業は経営者が高齢化している傾向にあり、健康上の理由でやむなく事業を閉じるケースも少なくありません。
こうした課題に対応するためには、事業承継の計画を早期に立てることや、経営を引き継ぐ人材を育成することが重要です。市場変化への適応力と、将来を見据えた承継戦略の両方が求められます。
なぜ、多くの起業が失敗するのか?主な原因トップ5

中小企業白書のデータなどから、失敗に至る典型的な原因を、以下の5例紹介します。
1.資金繰りの悪化とキャッシュフロー不足
売上が計画通りに伸びず、固定費や運転資金の支払いに追われる状況は、廃業の大きな要因です。特に創業初期は、予想外の出費や売上入金の遅延が資金ショートを招くことが多いため、キャッシュフロー管理の甘さが命取りとなります。
例えば、売上入金が月末締め翌々月払いという契約条件になっていると、2か月分の運転資金を事前に用意しておかなければなりません。この準備を怠ると、黒字経営でも資金不足で事業継続が困難になることがあります。
こうしたことから、ある程度の期間の固定費を賄えるだけの資金を確保したうえで、資金繰りの管理を十分に行うことが欠かせません。
2.市場ニーズの誤認と商品・サービスのミスマッチ
需要が少ない市場に参入したり、顧客が求めていない商品やサービスを提供したりすると、集客は困難になります。市場調査を軽視し、経営者の思い込みだけで商品を開発すれば、このリスクがさらに高まります。
たとえば、立地条件や価格設定が顧客層と合致していなければ、販促努力をどれだけ重ねても、思い通りの成果を出すのは難しくなってしまうでしょう。こうした失敗を避けるためには、事前に顧客インタビューや小規模な試験販売を行い、反応を確かめておかなければなりません。
3.マーケティング戦略や集客力の不足
商品やサービスの質が高くても、認知されなければ売上にはつながりません。特にデジタルマーケティングを十分に活用できていない場合、潜在顧客へのアプローチが不足します。限られた予算でも効果的な広告媒体やSNS、Webサイトを活用し、継続的に顧客との接点を増やす工夫が必要です。成功している企業は、広告費と売上の関係を分析し、費用対効果の高いチャネルに資源を集中させています。
4.経営スキルや意思決定能力の不足
経験不足や判断ミスは、資金や人材の浪費につながります。経営数字を正しく読み取る力、契約や法務の知識、戦略的な意思決定力など、経営者には多岐にわたるスキルが求められます。特に、情報不足のままで重要な判断を下してしまうと、後戻りができない状況に陥りかねません。これを避けるためには、経験豊富な専門家の助言を受けながら、正しい判断を下すようにしなければなりません。
5.人材確保・組織運営の課題
優秀な人材を採用し、長く働いてもらうことは簡単ではありません。人手不足や離職率の高さは、事業の成長を阻害します。採用活動では、給与や福利厚生だけでなく、働きやすい職場環境や成長機会の提供も重要です。また、採用後の教育や評価制度を整えることで、従業員のモチベーションを維持し、離職を防ぐことができます。
起業の成功率を高めるためのポイント

最後に、成功率を上げるための具体的なポイントについて解説します。
事業計画の精度向上とリスク管理
事業計画は、資金調達や企業経営の安定に直結します。したがって、市場規模や競合状況を正確に分析したうえで、正確な売上予測や利益計画を立てることが重要です。楽観的な予測だけでなく、悲観的なシナリオも用意し、想定外の事態にも備えておかなければなりません。さらに、固定費の削減や契約条件の見直しも、リスク管理の一環として効果的と言えるでしょう。
資金調達の工夫と安全余裕資金の確保
会社の資金基盤を安定させるためには、融資、出資、補助金など、複数の資金調達手段を組み合わせることが大切です。特に開業初期は、売上が安定するまでの間を乗り切るための運転資金を十分に確保しておかなければなりません。そのためには、できるだけ正確な資金繰り表を作成し、週単位で資金の動きを把握しておくと良いでしょう。
市場戦略の構築と専門家の活用
ターゲット市場を明確にし、競合との差別化を図る戦略を立てることが重要です。強みを生かせる市場でのポジショニングを固め、販売チャネルやプロモーション方法を最適化することが大切です。税理士などの専門家を活用し、経営判断の質を高めれば、リスクを軽減することができるでしょう。
まとめ
日本の起業成功率は国際的に見ても高めですが、長期的な継続には、資金、戦略、人材といった複数の要素を整えなければなりません。そのためには、具体的な数字で現状を正確に把握し、リスクへの備えを怠らないことが大切です。客観的かつ専門的な視点が必要であれば、専門家の助言を受けながら経営を進めて行くと良いでしょう。